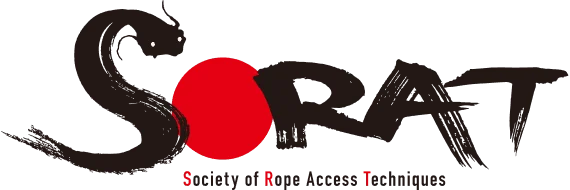ロープ高所作業★用語確認
— 基礎からわかる「ロープ高所作業」と【SORAT】技術 —
ロープを使った高所作業や点検には、さまざまな専門用語があります。
ここでは、インフラ点検の現場でよく使われるキーワードを整理してご紹介します。
『ロープ高所作業』
定義:2016年(平成28年)の改正安衛則(労働安全衛生規則)で、初めて法的に定義された作業。
高所や難所において、足場・高所作業車などを使用せず、ロープを用いて安全を確保しながら行う作業を指します。
同改正で、「ライフライン(命綱)」の設置も義務化されました。
『ロープ高所技術』
定義:ロープ高所作業を行う際に用いるロープ技術。
同義語:ロープアクセス技術
安全確保や移動、姿勢保持のためのロープ操作全般を指し、作業の目的に応じて多様な技術体系が存在します。
代表的な技術として、【親綱・ロリップ】技術、IRATA/SPRAT技術、そして日本独自の【SORAT】技術があります。
『ロープ高所点検』
定義:ロープ高所技術を用いて、高所・難所で構造物などの点検を行う作業。
同義語:ロープアクセス点検
略称:ロコテン(ROKOTEN)
道路橋やダム、トンネル、のり面など、通常の手段では近接できない箇所の点検に用いられます。
点検者自身が構造物に接近し、近接目視・接触観察を行うのが特徴です。
『空人(そらっと)/空子(そらこ)』
広義の意味:ロープ高所作業を行うすべての作業者(ロープユーザー)のこと。
狭義の意味:3次元ロープアクセス技術【SORAT】の達人を指します。
現場では、「空を舞うように移動する技術者」という意味を込めて、この愛称で呼ばれています。
【SORAT】技術
正式名称:3次元ロープアクセス技術【SORAT】(エスオーアールエーティー)
開発:(株)きぃすとん
技術管理・普及:(一社)ロープアクセス技術協会(略称:SORAT/Society Of Rope Access Techniques)
【SORAT】技術は、インフラ点検を目的として開発された日本発・世界唯一の3次元ロープアクセス技術です。
-
上下・左右・前後の全方向に安全・迅速・確実に移動可能
-
技術の根幹となる『2点確保』により、安全と機動性を両立
-
35年間、無事故の安全実績を継続中
高度なロープ技術と確かな点検技術を融合させたこの技術は、世界中のどの手法にもない“日本独自の誇るべき技術”です。
まとめ
『ロープ高所作業』や『ロープ高所点検』は、単なる危険作業ではなく、高度な技術・経験・安全管理のもとで成り立つ専門職です。
そして、その頂点に位置するのが【SORAT】技術。
きぃすとんでは、【SORAT】技術を軸に、全国のインフラ点検現場で“空を駆ける点検技術者=空人(そらっと)”たちが、安全と信頼を支え続けています。